
雪がシンシンふる晩でございました。
信州の山おくに年老いた夫婦が住んでおりました。夫婦は子宝にめぐまれず、二人肩をよせあってひっそりと暮らしておりました。
そんなある晩のことでございます。
「じいさま。起きてくださいよ」
おばあさんは、となりに寝ていたおじいさんの肩をゆすった。
「どうしたんじゃ。ばあさまや」
「さっきから、家の外から赤児の泣き声のようなものが聞こえるんじゃ」
「そんなことあるめい。ばあさまや、それは風の音じゃで」
「じいさま。しずかに」
おじいさんが耳をすませると、ヒュー、ヒューという風の音にまじって、かぼそい赤児のなく声がした。
「たしかに。赤児の声じゃ」
おじいさんはブルッとみぶるいしたが、布団からとびおきると綿入れをはおり土間にかけおりた。木戸をあけると白い雪が音をたてて舞いこんだ。おじいさんはあまりの寒さに歯をガチガチならしたが、手をグッとにぎると外に飛び出した。赤児は白いおくるみにつつまれて庭の梅の木のもに捨てられていた。赤児のからだには、たくさんの雪がつもっておった。
「だれが、こんなむごいことを」
おじいさんは赤児をだきあげた。
赤児はおじいさんの顔をみると声をたてて笑った。
赤児は雪のような真っ白な肌をしておった。いや、髪も瞳も真っ白じゃった。
「ばあさまや。赤児じゃわい」
おばあさんは、急いでお湯をわかした。
「まあまあ。かわいそうにのう」
おばあさんは赤児のそばに寄って、おくるみの中の雪のように白い子供をみて驚いた。
「じいさま。この子は」
「梅の木のもとに置き去りにされておった」
おじいさんは赤児をいろりのそばに連れていった。すると、赤児は火をつけたように、泣き出した。おじいさんは赤児をあやしながら、部屋のすみずみまで歩いたがいっこうに泣きやまなかった。だが寒い土間にきたら、赤児は笑いだすのだった。
「ばあさまや。この子はおなかがすいているのじゃろう。食べる物は残っておらんかの」
「ヒエ粥ならありますじゃ」
「ヒエ粥か。くわんよりか、ましじゃろ」
おばあさんは大事にとっていたヒエ粥をあたためはじめた。
赤児はいろりのそばに連れていくと泣くので、おじいさんは寒い土間で赤児の口に粥を入れようとすると、赤児はいやがって食べなかった。
「どうしたんじゃろう。困ったもんじゃな」おじいさんは心配そうな顔をした。
「ひょっとして、この子供は」
おばあさんはそうゆうと外にとびだして、手にひとつかみの雪を持ってきた。おばあさんは雪を赤児の口をはこぶと、赤児は美味しそうにたべた。
「やはり、思ったとおりだ」
おばあさんは顔をしかめた。
「じいさまは雪女の話を聞いたことがあるかね」
「ああ。そんなら聞いたことはある」
「じゃ。雪ん子の話はどうじゃ」
「それはしんねえ」
「じゃ、はなして聞かせよう。おらが子供だったときに本当にあったはなしだ。 おらが十のときに、一ノ谷に若夫婦がすんでおった。夫婦には子供がおらんかった。雪山に猟にいった主人がおんなの赤児を拾ってきた。赤児はなんでも野道に捨てられていたそうで、ふびんにおもった若夫婦はじぶんの子供として育てた。赤児は髪も目も肌も真っ白じゃった。それも、この子とおなじように火をとても嫌ったそうじゃ。赤児は雪しかくわんかったが、どんどん大きくなり、ひと冬で娘になった。夫婦はおそろしゅうなって娘を山に捨てにいった。それからじゃ。夫婦も娘の姿も見えんようになったのは。村の衆はいった。娘は雪女で、夫婦はとってくわれたじゃと」
「ばかばかしい」
「それじゃ。じいさまは、そのはなしを信じないとゆうのかい」
おじいさんは、返事をしなかった。
「じいさま。悪いことはいわん。この子は人ではねえ。はよう山に捨ててくることじゃ」
おじいさんは困った顔をして、
「ばあさまや。もう少し様子をみよう。もしも雪ん子なら、おらがお山に捨てに行くから」
おじいさんは、赤児におユキとゆう名前をつけ、とてもとても、かわいがった。おユキはみるまに成長して晩冬には少女になった。おばあさんは、おユキがおそろしくてならんかった。
「おユキよ、ばばの願いを聞いてくれるか」
おユキはうなずいた。
「マキがのうなったので、山からマキをとってきてくれないか。マキは必ず乾かしてくるんじゃよ。それと、マキはかならず猿の沢でとるのじゃよ」
猿の沢は、冬場は猟師でも行けないような奥山にあり、少女の足てはたどりつくのがやっとだった。おユキはうなずくと、ちいさな背中にしょいこをせおって雪の山道をすすんでいった。
「これで、あん子は帰ってこれんじゃろう」
おばあさんは、胸をなでおろした。
そうこうするうち夜になった。
「おユキはどうしたんじゃろう」おじいさんが言った。
「おら、しんねえ」おばあさんは、しらん顔じゃった。
おじいさんはやさしい人なので、おユキがいないのをたいそう心配した。
もうすっかり日も暮れた。おばあさんはフトンにもぐりこんだが、おじいさんはいろりの側でおユキの帰るのをまった。
「じいさま。おユキは雪ん子じゃけん、お山に帰ったんじゃねえのか」
「お山にか」
「そうじゃ。かかさまのいるお山じゃ」
すると、なにやら外から足音がした。
「おユキじゃ。おユキが帰ってきた」
おじいさんは土間にかけおりると木戸をあけた。おユキは、小さいせなかに、乾いたマキをたくさん積んでいた。
「どうしたんじゃ。こんなに、おそくまで」
「心配かけてごめんなさい。拾ったマキを火で乾かしていたんで、おそくなったのです」
「おユキよ、ばばの願いを聞いてくれるか」
「はい、おばあさま。どのような事でしょうか」おユキは言った。
「今夜権現さまの火祭りがある。権現さまはそれは立派な神様で、人をたぶらかす悪い魔物を退治してくれる神様じゃ。おユキよ権現さまのたいまつの火をこのわらで編んだひもにうつして、かまどに火をおこしてくれないかい。そうすれば無病息災になるそうだ。それと、一晩中かまどの前で火の番をするのじゃよ。わかったか」
おユキはうなづくと旅装束に着替え、もらい火用のわらのひもを手ににぎった。その晩、おユキの帰りが遅いのでおじいさんはおばあさんへ聞いた。
「おら、しんねえ」おばあさんは、しらん顔じゃった。
「雪女め。今度こそ、権現さまのお力で、無事にはすみますまい」
おじいさんの声でおばあさんは飛び起きた。
おユキが、かまどの前で倒れていたのだ。おユキはいつもは近づかないかまどに火をつけて番をしていたらしい。おばあさんは、大声をあげると寝込んでしまった。おユキがいくら看病しても、おばあさんの病気はよくならなかった。
「おばあさま。お体の具合はどうですか」
おばあさんは、おユキに背中を向けると、
「おユキよ。おらは、じき死ぬ」
「そんな事ないですよ。気をしっかりもって下さい。」
「春はまだかな。せめて、死ぬ前に梅の花のにおいをかぎたいもんだ」
「梅の花の香りですか」
「そうじゃ」おユキは一瞬ためらったが。
「判りました」
とそう言うとおユキは外にかけだした。おユキは雪女の姿になると、手あたりしだいに、あたりものを凍らせはじめた。それとみたおじいさんとおばあさんは手をとりあってブルブルふるえた。
するとどうじゃろう。
今まで凍った木々からすーと雪が消えると、一羽のうぐいすが飛んできた。
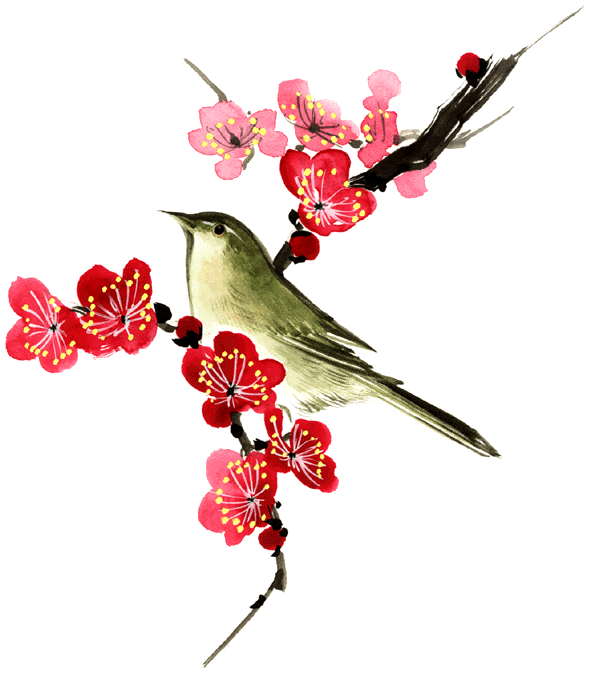
うぐいすは梅の枝にとまった。おユキはその下にいた。
ホーホケキョ
ドス
おユキの腕がとけてなくなった。
ホーホケキョ
ドス
おユキの足がとけてなくなった。
ホーホケキョ
ドス
おユキの体がとけてなくり、あとは、首しか残っておらんかった。
おユキの首はふたりに微笑むと、
「おじいさま、おばあさま。今までお世話になりました。わたしは春になると生きられません。これからも、ふたりなかよく、くらしてくださいね」
おじいさんと、おばあさんは、うなずいた。
「ありがとう」そう言うとおユキの頭は溶けて、あとには水たまりしか残らんかった。
おじいさんは、おばあさんの手をにぎると、
「ばあさまや、あの子は、わしらのたからじゃったの」と言った。
おばあさんは、ただ、うなずくばかりで、目から涙が洪水のようにあふれた。
それから、おじいさんとおばあさんのすむ山里だけが、春のくるのが早くなったそうだ。 おしまい
あとがき
この作品は二十年程前に作ったもので、未完成になっていたものを加筆修正したものです。
今回はどんは作品にしようか、構想をねればねるほどわからなくなって、やむなく昔の作品の手直しという型になりました。小説を書き始めた頃は、自分が偉く思えていて、何を書いても、すばらしいとうぬぼれておりましたが、最近見直したら下手すぎてガッカリしました。でも、何かを書こうとするバイタリティを感じます。その思いを忘れないようにしたいと思うこの頃です。 北原 文絵
そのリンです。
この作品は、いまから、数年前に同人誌に掲載したものです。
北原 文絵は、ペンネームで絵本作家になるのが夢だったので、文も絵も北原さんですよと、いう意味です。
ひ、ひどい。改めて読むと、手直ししたくなります。ひどい状態ですが、趣味なので掲載します。(2007年2月5日)